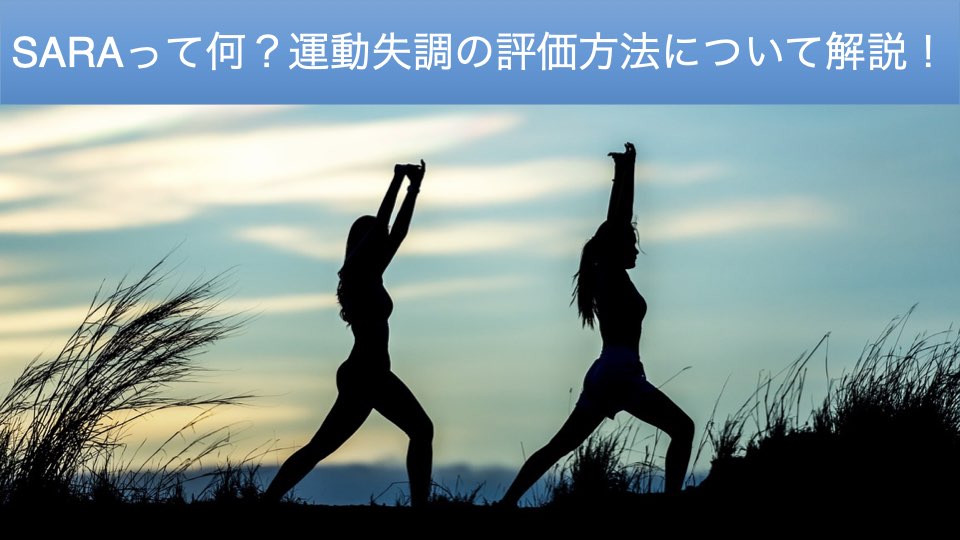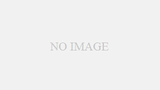SARAとは、脊髄小脳変性症などの運動失調の重症度を定量的に評価するツールです。
この記事では、SARAの評価項目や活用方法、利点と欠点について解説します。
SARAを使えば、運動失調の様々な側面を客観的に把握し、治療の効果を確認することができます。
SARAの定義と背景
SARAとは、Scale for the Assessment and Rating of Ataxiaの略で、脊髄小脳変性症の患者の運動失調を評価するために開発された評価方法です。脊髄小脳変性症とは、脊髄や小脳などの神経細胞が変性することで、歩行や姿勢、言語などに障害が生じる疾患です。
SARAは、8つの評価項目から構成されています。姿勢と歩行、伸筋運動、指の追随運動、運動の調整、発声などが評価され、各項目には0から2のスコアがつけられます。最大スコアは40点で、スコアが高いほど、患者の運動失調が深刻であることを示しています。
SARAの評価項目
SARAは、以下の8つの評価項目から構成されています。
- 歩行
- 立位
- 座位
- 言語障害
- 手の回内外運動
- 鼻指試験
- 指追い試験
- 膝-踵試験
各項目には設定された点数(たとえば0〜8点など)があり、総合点は最大40点です。得点が高いほど運動失調の重症度が高いことを示します。
SARAの活用方法
SARAは、従来の運動失調評価法に比べ簡便かつ迅速に実施でき、検者間や検者内の信頼性・妥当性も高いとされています。具体的な活用例は以下の通りです。
研究における活用 学会発表や論文でも、SARAを用いた定量評価が増えており、運動失調の様々な側面を客観的に評価する手段として注目されています。
治療効果の評価 治療前後でSARAの総合点を比較することで、患者の運動失調が改善、安定、または悪化しているかを定量的に把握できます。
日常生活動作との相関評価 SARAの総合点は、Barthel Index(BI)などの日常生活動作の自立度評価と相関があり、治療計画の策定やリハビリテーションの進捗把握に役立ちます。
SARAの利点と欠点
【利点】
- 簡便性と迅速性 約10分程度で実施可能で、特別な機器を必要としません。
- 高い信頼性と妥当性 検者間、検者内の一致度が高く、運動失調の重症度やADLとの相関性も確認されています。
- 治療効果の評価が可能 治療前後の変化を定量的に捉えることができ、リハビリテーション法の選択に役立ちます。
【欠点】
- 神経学的背景の評価ができない SARAは症状を定量化する一方、運動失調の原因や病理学的背景については評価できません。
- 質的側面が捉えにくい 患者の主観的な感覚や生活の質、感情面については別途アンケートや自己評価が必要です。
- 適用範囲の限界 主に小脳性運動失調の評価を目的として開発されているため、眼球運動や顔面の微細な運動障害など、一部の症例には適さない場合もあります。
SARAのカットオフ値について
(~運動失調の重症度に基づいた歩行予後予測の視点~)
臨床現場では、SARAの総合点を用いて患者の歩行能力や自立度を予測する際、どの得点を基準(カットオフ)とするかが重要な課題となります。最新の文献では、対象となる患者の状態・入院時期によって異なるカットオフ値が提案されています。
1. 急性期脳血管疾患患者の場合
宮澤らによる報告(第50回日本理学療法学術大会,東京)では、急性期における脳血管疾患患者を対象とし、SARAの歩行項目に着目して評価を行いました。
- カットオフ値:8点 この研究では、SARAの総合点が8点以下であれば独歩可能群、8点を上回る場合は移動介助を必要とする群に分類されました。 ※ただし、このカットオフ値は急性期という短期的な評価に基づいたものであり、患者の状態やリハビリテーションの進捗に応じた判断が求められます。
2. 回復期病棟における小脳性運動失調患者の場合
石川らによる回復期病棟での研究では、入院時のSARA得点から退院時の歩行自立の予測を試みました。
- カットオフ値:18.5点 ROC曲線解析を用いた結果、入院時のSARA得点が18.5点を上回ると退院時に歩行自立が困難である可能性が高いことが示されました。
- 感度:0.88
- 特異度:0.89
- AUC:0.97(95%信頼区間:0.57−0.98) この高精度な予測モデルは、回復期の運動失調患者において、早期の治療計画や在宅復帰の準備を進める上でも非常に有用です。
3. カットオフ値の選定は状況に応じて
同じSARAでも、対象となる患者(急性期 vs. 回復期、脳血管疾患 vs. 小脳性失調)や評価の目的(歩行自立の予測、治療効果の評価など)により、適用すべきカットオフ値は異なります。 したがって、臨床現場でSARAを活用する際は、患者の状態や病棟の特性に応じた基準の設定が必要です。各施設や研究におけるデータをもとに自己の臨床判断と照らし合わせながら運用することが求められます。
SARAの使用例と今後の展望
従来の運動失調検査(例:指鼻試験や指追い試験)は、結果が陽性か陰性かで判断されることが多く、定量的な評価が難しいという点で課題がありました。
一方、SARAは定量化されたスコアにより、治療効果の変化やリハビリテーションの進捗状況を明瞭に示すため、臨床研究や日常診療の双方で注目されています。
また、今回ご紹介したカットオフ値の事例は、歩行自立や在宅復帰に向けたリハビリテーション計画の立案に大いに参考となるでしょう。
将来的には、より多くの症例データを蓄積することで、さらに個々の患者に合わせた精度の高い評価基準が確立されることが期待されます。
まとめ
SARAは、脊髄小脳変性症やその他の運動失調に対して、短時間で信頼性の高い評価が可能なツールです。
- 活用方法としては、治療効果の定量的評価や日常生活動作との関連性の把握があります。
- 利点・欠点を正しく理解しつつ、患者の個々の状態に合わせた評価が求められます。
- カットオフ値の設定については、対象となる患者層や評価目的により異なるため、急性期では8点、回復期では18.5点という具体的な事例を参考に、臨床現場での柔軟な運用が重要です。
SARAの評価を通じて、運動失調の改善に向けた最適な治療計画の策定やリハビリテーションの効果測定に役立てていただければ幸いです。
SARA評価用紙(PDF)
SARAの評価項目について詳しく知りたい場合は、以下のPDFをご参照いただけましたら幸いです。ぜひ、SARAを使って運動失調の評価を行ってみてください。SARAを活用すれば、運動失調の改善に役立つ治療法を見つけることができるかもしれません。
参考文献
- 宮澤 佑治, 新屋 順子, 土屋 忠大, 澤下 光二. ScalefortheAssessmentandRatingofAtaxia(SARA)を用いた急性期脳血管疾患患者の失調症における歩行能力の検討. 第50回日本理学療法学術大会
- 石川真衣, 早川佳伸, 福井裕介, 磯兼直道, 秋本真央, 土屋晶敬. 回復期病棟における小脳性運動失調患者の歩行の予後予測について ~運動失調評価指標(Scale for the Assessment and Rating of Ataxia)を用いた検討~. 愛知県理学療法学会誌, 第30巻 第2号, 2018年12月, pp.88–91.